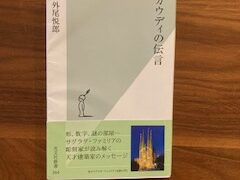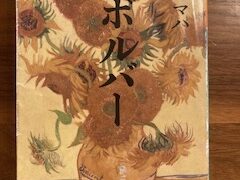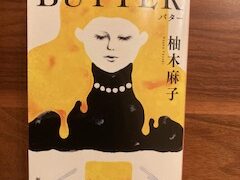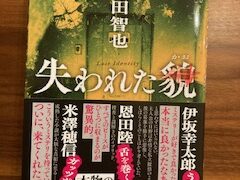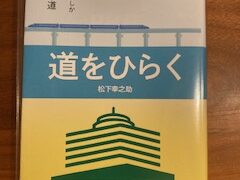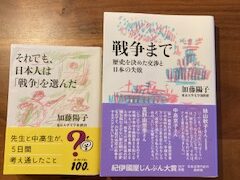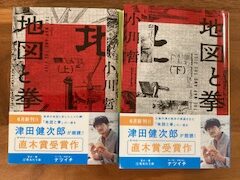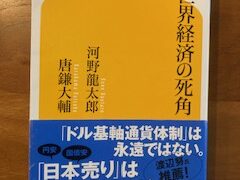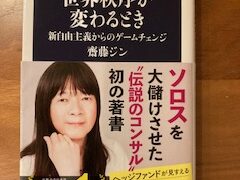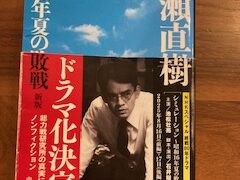 読書三昧
読書三昧 【おすすめ書籍 92】猪瀬直樹『昭和16年夏の敗戦』(中公文庫)
NHKスペシャル 終戦80年ドラマ「シミュレーション~昭和16年夏の敗戦~」の放送がきっかけに、原作の本書が2025年話題になりました。単行本初版が1983年。著者猪瀬直樹氏30代の作品です。その後1987年に『ミカドの肖像』で大宅壮一ノンフィクション賞を受賞するという脂が乗った時期の一作です。総力戦研究所の若きエリートたちによる模擬内閣が出した「日本必敗」の進言は無視され、なぜアメリカと開戦してしまったのか・・・。著者によるあとがきや石破茂氏との巻末対談の最後まで読み応えがあります。当時から政治家の中でも特に石破氏が本書の内容に非常に関心を示していたことが巻末対談でわかります。2025年石破茂前首相は戦後80年に「談話」ではなく「所感」を総理退任前に出しましたが、なぜ出すことに拘ったのか、またその全文から彼の歴史認識を含め、並々ならぬ思いも伝わってきます。