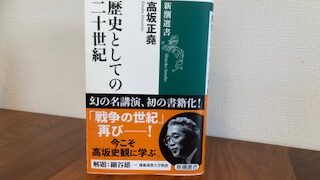 読書三昧
読書三昧 【おすすめ書籍 54】高坂正堯『歴史としての二十世紀』(新潮選書)
ウクライナ戦争やイスラエルによるパレスチナガザ地区への侵攻など戦争が続いているこの時代に、『国際政治』や『文明が衰亡するとき』の著者生前の名講演が書籍化されました。「〈いい人〉の政治家が、なぜ戦争を起こすのか」「ロシアに大国をやめろと強制することはできない」氏が語る「戦争の世紀」が再来した今、あらためて高坂史観を学ぶ人が増えてほしいと思える一冊です。
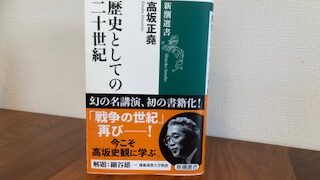 読書三昧
読書三昧 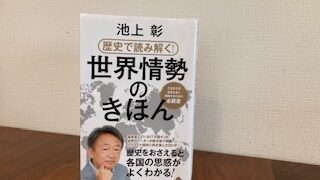 読書三昧
読書三昧 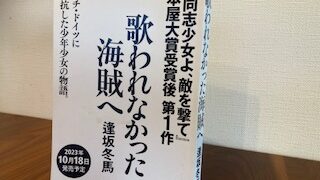 読書三昧
読書三昧 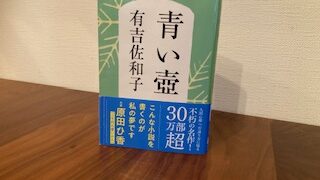 読書三昧
読書三昧 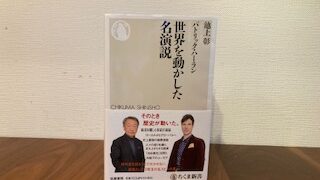 読書三昧
読書三昧 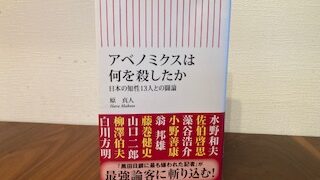 読書三昧
読書三昧 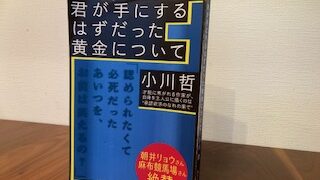 読書三昧
読書三昧 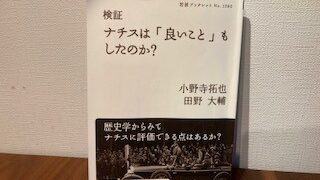 読書三昧
読書三昧  読書三昧
読書三昧 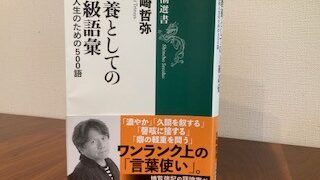 読書三昧
読書三昧